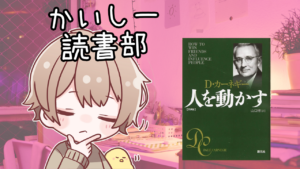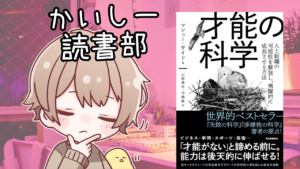艱難汝を玉にす(読み方:かんなんなんじをたまにす)とは、「人間は多くの苦しみや困難を経て初めて立派な人間になる」という意味の諺です。
「掘り出された玉は、始めは粗くても磨けば輝く」ということを意味しています。
「若い時の苦労は買ってでもせよ」や「苦労屈託身の薬」と同じような意味で使われることが多いですね。
今回は、艱難汝を玉にすの意味や由来について説明をしたいと思います。
「艱難汝を玉にす」の由来
艱難汝を玉にすは、フランスの「Vent au visage rend l’homme sage」が由来となっています。
逐語訳すると「逆風は人を賢くする」です。
漢文っぽい訳し方をしているので中国が由来であると思ってしまいますが、実はフランスの諺が由来なのです。
16世紀のガブリエル・ムーリエの諺集に「Vent au visage rend l’homme sage」という言葉が登場しているので、少なくとも16世紀末よりは前から存在している諺であることが分かります。
フランスの「Vent au visage rend l’homme sage」が直接日本に伝わったのではなく、この諺はアメリカに「Adversity makes a man wise」として英訳されてから、日本に伝わりました。
「Adversity makes a man wise」を直訳すると「逆境は人を賢くする」という意味であり、フランスの「逆風は人を賢くする」とほぼ同じ意味ですね。
この「Adversity makes a man wise」が遅くても19世紀末の明治時代に日本へ伝わり、「艱難汝を玉にす」という諺になりました。
「艱難汝を玉にす」は、戦前の教育勅語における修身(現代での道徳にあたる)の教科書に1期〜4期にかけて載っていたためか、「人間は多くの苦しみや困難を経て初めて立派な人間になる」というように、元となったフランスやアメリカの諺よりも道徳的な意味合いが強い諺になっています。
「艱難汝を玉にす」の使い方
この言葉を座右の銘にしたり、自分の生き方や考え方の芯としている人もいるのではないでしょうか。
「艱難汝を玉にす」の使用例としては
・艱難汝を玉にすと言うように、困難がやってきても立派な人間になる機会をいただいたと思い頑張りなさい
・あなたが素敵なのは、艱難汝を玉にすと言うように辛く苦しい過去を乗り越えたからだ
等でしょうか
「辛く苦しい困難があったとしても、乗り越えることでより良い人になれる」
ということを伝えたい・主張したいときに、艱難汝を玉にすという言葉を使いましょう。
また、困難を乗り越えたことで今の自分があると思っている人は、座右の銘にしてもいいかもしれませんね。