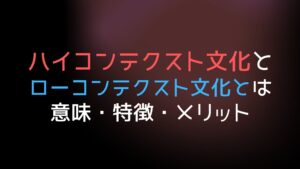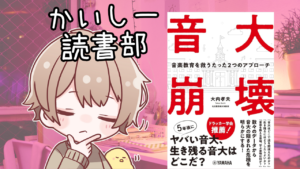私たちは普段、日用品や食品の値上がりをよく気にしています。
野菜や卵の値段の変動に敏感な人は多いのではないでしょうか。
消費者としては商品を安く買いたいところですが、人件費や原材料の高騰、消費税増税による消費の低迷等から値上げを余儀なくされる企業も多いです。
今回は、企業の苦肉の策であるシュリンクフレーションについて、わかりやすく簡単に説明していきます。
シュリンクフレーションとは
シュリンクフレーションとは、shrink(縮小)とInflation(インフレ)を組み合わせた造語で、商品の値段を変えずに中身を減らすことで実質的に値上げを行うことです。
あからさまに値上げをすると購買意欲が薄れてしまうため、消費者に気付かれないように値上げをするという苦肉の策ですね。
値上がりしていることに気付きにくいことから、ステルス値上げと呼ばれることもあります。
シュリンクフレーションの具体例
シュリンクフレーションの具体例は、いつの間にか容量が減っている商品wikiを見ることで確認することができます。
その中でもシュリンクフレーションの具体例をいくつか紹介をします。
じゃがりこ カルビー

| 2007年以前 | 65g | 89円 |
| 2007年 | 60g | 89円 |
サラダチキン セブンイレブン

| 2015年以前 | 125g | 198円 |
| 2015年頃 | 115g | 198円 |
| 2019年頃 | 110g | 198円 |
なっちゃん サントリー
![]()
| 2011年以前 | 500ml | 140円 |
| 2011年 | 470ml | 140円 |
| 2014年 | 450ml | 140円 |
| 2015年 | 430ml | 140円 |
| 2017年 | 425ml | 140円 |
カントリーマアム 不二家

| 2005年 | 30枚 | 323円 |
| 2007年 | 28枚 | 323円 |
| 2008年 | 24枚 | 323円 |
| 2011年 | 22枚 | 323円 |
| 2014年 | 20枚 | 323円 |
| 2016年 | 20枚(1枚あたりの容量減) | 323円 |
このように、様々な商品で”ステルス値上げ”が行われています。
特に、カントリーマアムは10年かけて10枚も減っていたんですね。
シュリンクフレーションが非常に身近にあることが理解できたのではないでしょうか。
これら以外にも様々な例があるので、いつの間にか容量が減っている商品wikiを見てみるのも良いでしょう。
シュリンクフレーションの言い訳
消費者に気付かれにくいことから”ステルス値上げ”と言われていますが、値上げの際に企業が公式にコメントしている場合も少なからずあります。
言い訳という言い方は良くないかもしれませんが、企業がよく言う言い訳は
「自助努力のみでは価格維持することが極めて困難になった」
「どうしても容量を少なくせざるを得なかった」
「容器を持ちやすい形に変更しました」
「リニューアルを行った」
等ではないでしょうか。
最近だとセブンイレブンの値上げのコメントが面白く、よくネットで見かけるような気がします。
ある意味、企業努力なのかもしれませんね。
シュリンクフレーションは違法なのか?
シュリンクフレーションは違法ではありません。
商品の容量を変えたり値段を変更したりするのは普通のことで、違法ではありません。
しかし、様々なシュリンクフレーションが当たり前のように行われているせいで、消費者からのイメージが悪くなったり一部で問題になったりしていることもあります。
素直に値上げをすると注目を浴びてしまうため、ステルス値上げをする方が話題にならず済んでいるのではないでしょうか。
実際、パッケージの縮小や容器の底上げが一部で話題になっているにも関わらず、シュリンクフレーションという言葉を知らない人は多いです。
どこかで問題が大きくならない限り、違法になることはないでしょうね。

テクノロジーのプレゼンテーション.png)
テクノロジーのプレゼンテーション-300x169.png)