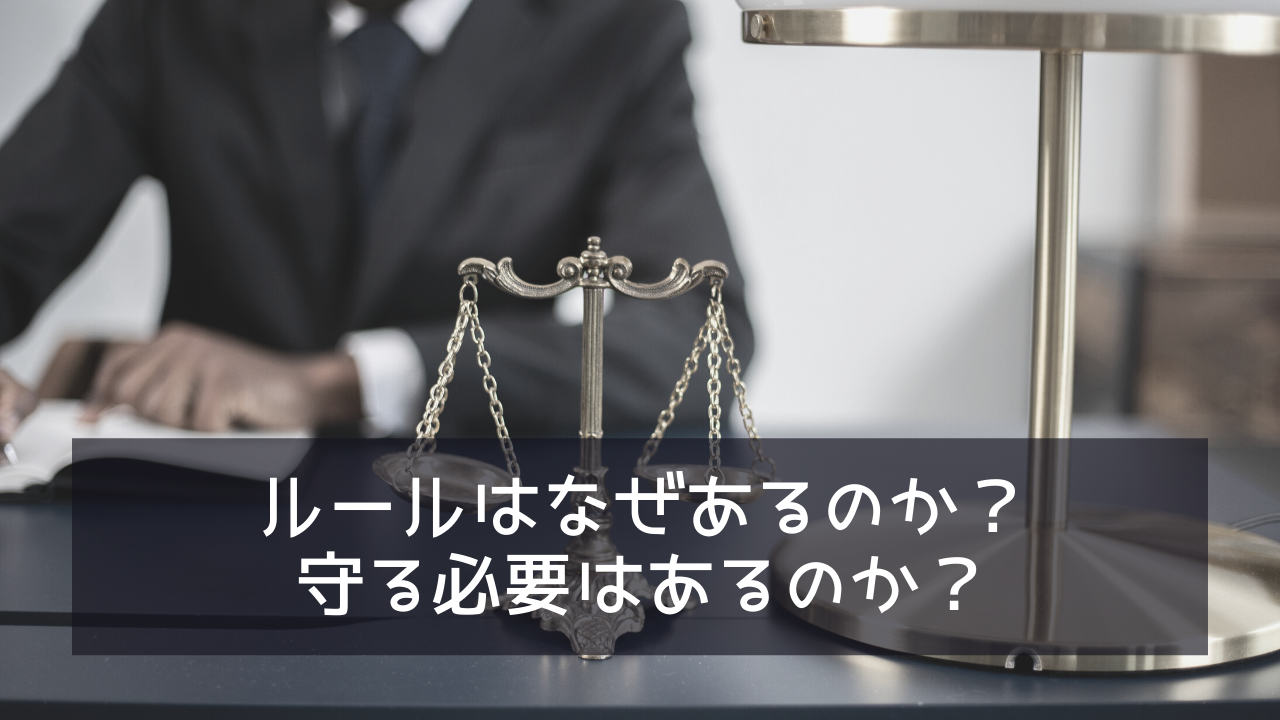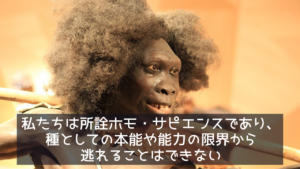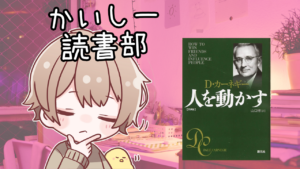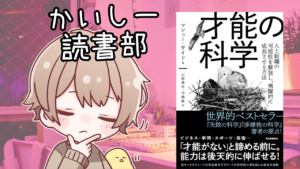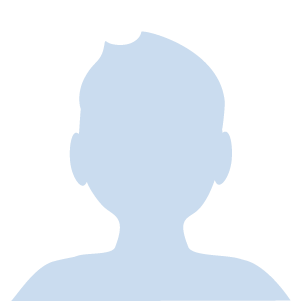 男性
男性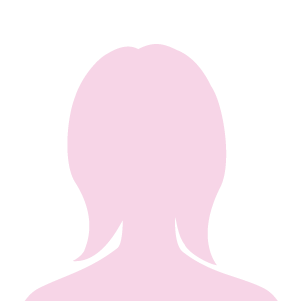
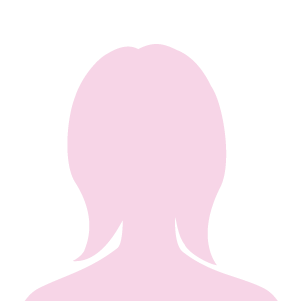
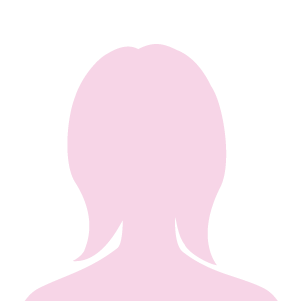
と思ったことはありませんか?
「ルールだから守らなければいけない!」
「ルールを守らないなんて信じられない!」
正直、うざったいと思うこともありますよね。
今回は、「ルールはなぜあるのか?守る必要はあるのか?」について、精神論・感情論ではなく、冷静に・論理的に考えをまとめたいと思います。
ルールとは何か
ルールとは何か
「ルールとは何か」と聞かれると、下記のようなものを思い浮かべるのではないでしょうか。
「この銭湯では、タトゥーを入れてる人の出入りを禁止にしている」
「車の速度制限」
「金髪は校則違反だ」
「コロナ禍ではマスクをしましょう」
例えば、バレーボールについて考えてみましょう。
バレーボールでは下記のような「何かを制限・禁止する」ルール以外にも、
連続してボールに2回触れてはいけない
同じチームでボールに触れていいのは3回まで
ネットに触れてはいけない
下記のようなルールも存在します。
人数は6人(6人制)
1試合5セットマッチ、25点先取で1セット
ネットの高さは男子2.43m、女子2.24m(6人制)
コートの広さは18m×9m
ルールにはこれら以外にも、マナーや道徳規範等、様々な種類のものが存在していますが、この記事では、ルールの中でも「何かを制限・禁止にするもの」をルールとして、話を進めたいと思います。
守らなくて良いルールはルールではない
守らなくても良いルールはルールではありません。
連続してボールに2回触れてはいけない
このルールを守らなくても良い状態を想像してみて下さい。
連続してボールを触ってもペナルティがない、誰も指摘しない、皆連続してボールを触っている…ルールが存在している意味、全くないですよね。
ルールは守られることによって存在を維持できると考えることができます。
ルールはなぜあるのか
ルールはなぜあるのでしょうか?
その理由を考えてみます。
存在を定義するため
先程と同様に、バレーボールを例にして考えていきましょう。
バレーボールにはというルールが存在しています。
連続してボールに2回触れてはいけない
同じチームでボールに触れていいのは3回まで
ネットに触れてはいけない
なぜ上記のようなルールがあるかというと、それは、バレーボールは「そういうスポーツだから」です。
連続して何度でも触っていい
5回で返してもいい
ネットに思いっきり触っても良い
このようなルールの場合、果たしてそれはバレーボールと言えるのでしょうか?
小学校の授業でバレーボールを行う場合は上記のルールを破ってもバレーボールといえるかもしれませんが、プロの試合や大会では上記のルールを守らなけらばバレーボールといえないでしょう。
“バレーボール”という時点で、上記のルールが存在するのです。
つまり、ルールは、スポーツなどの行為の存在を定義するために必要であると言えます。
ルールは、スポーツなどの行為の存在を定義するために必要。
なお、「バレーボール」の時点で「連続してボールに2回触れてはいけない」のですが、どうしても勝ちたくなってしまい、つい連続して触ってしまう場合もあるかもしれません。
そのような場合を考慮して、「連続してボールに2回触れてはいけない」等のルールを明記していると考えられます。
目的を遂行するため
次に、学校の授業を例として考えてみましょう。
例えば、
「授業を遅刻してはいけない」
というルールのある学校は多いですよね。
さて、なぜ「授業を遅刻してはいけない」というルールは存在しているのでしょうか?
その理由は、授業を受けて、授業の目的を達成するためです。
授業の目的は「何かを知る・理解する・身につけ・自身の価値を高める」、つまり、「学ぶ」ことにあります。
授業に遅刻すると学ぶ機会が失われ、目的を達成できなくなってしまいますよね。
つまり、ルールは、授業等の行為を通して目的を遂行するために必要であると言えます。
ルールは、共通の目的を達成するために必要
ルールを守る必要はあるのか
ルールとゲーム
バレーボールにはルールがあり、授業にもルールがあります。
ルールはルール単体で存在できず、バレーボールや授業のような「ゲーム」を行うために、ルールが存在していると考えられます。
「連続してボールに2回触れてはいけない」のは、バレーボールを行うためのルールですし、「授業を遅刻してはいけない」のは、授業を行うためのルールなのです。
日本で生きてくためのルール
スポーツをするためのルール
学校で生活するためのルール
旅行をするためのルール
車を運転するためのルール
ルールは何かしらのゲームを遂行するために存在していると言えます。
ルールを守る必要はあるのか?
バレーボールの目的は「勝利」することであり、授業を受ける目的は「学ぶ」ことです。
(他にも目的はありますが、とりあえず「勝利」と「学ぶ」ことを目的として考えます)
連続してボールに2回触れるとポイントを取られてしまい、勝利から遠ざかってしまいます。
授業を遅刻すると授業の時間が少なくなってしまい、学びから遠くなってしまいます。
つまり、バレーボールや授業の目的を達成するため、ゲームの目的に沿ったルールは守る必要があるのです。
バレーボールを皆で行うために、ボールを連続で触っちゃいけない等のルールを守る必要がある
逆に言うと、目的を達成することに関係ないルールは守る必要性を感じることが難しくなってしまいます。
授業中にくしゃみは3回まで
というルールがあった場合、守る必要性を感じるでしょうか?
感じませんよね。
ルールは常に良いものとは限りません。
極端な話ですが、就職した会社に「組織的犯罪を行うために協力しなければならない」というルールがあった場合、ルールを守る必要はあるあのでしょうか?
場合によっては、ルールを守らない方が良いかもしれませんね。
上記の例は、会社のルールを守ると法律を破ることになり、会社のルールを破ると法律を守ることになるという構造的に面白い状態になっています。
解説すると長くなってしまうので、さらに踏み込んで解説するのは避けることにします。
意味のないルールや、守らない方が良いルールもある
意味のないルールとはどんなルールか
目的を達成することに関係ないルール
上記の通り、目的を達成することに関係ないルールが「意味のないルール」です。
「バレーボールの練習中、必ず青汁を飲むこと」
なんてルールがあったら、どう思いますか?
「どうしてこんなルールがあるのか」を説明できない限り、守る意味を感じることができませんよね。
ルールを守る人にとって、意味のないルールと感じてしまうのです。
しかし、意味のないルールであると感じても、あなたがルールの意味に気付いていないだけかもしれません。
ルールの意味が分からなかったら、ルールを守らせる立場にある人に意味を聞いてみてください。
ルールの意味をきちんと答えることができ、一般的に理解できる内容であれば、それは意味のあるルールです。
ルールの意味を答えられない、一般的に理解されない内容であれば、意味のないルールでしょう。
目的を達成することに関係のないルールは、意味のないルール
守ることよりも破ることの方が利益のあるルール
守ることで得られる利益 < 破ることで得られる利益
である場合、ルールの意味がなくなってしまいます。
学校の授業は「学ぶ」ためにあるものです。
しかし、教えるのが下手すぎて受ける価値のない授業の場合、授業を休み自分で勉強した方が、より「学ぶ」ことができるかもしれません。
まさに、「守ることで得られる利益 < 破ることで得られる利益」であると言えるでしょう。
コロナ禍の飲食店等の休業要請も、典型的な例なのではないでしょうか。
始めの頃は「休業しないと感染してしまう」ことを心配し、休業していた人が多かったと思います。
しかし、「営業再開してもコロナに感染しない、感染したとしても助かる可能性が高い、休業しても大してお金が貰えない」と思ってしまうと、休業要請を断ることで得られる利益の方が多くなると考えてしまうです。
つまり、休業要請は、様々な人にとって「意味のないルール」となってしまったのです。
守らない方が得をするルールも意味のないルール
まとめ
ルールは、バレーボールや授業等のゲームの目的を達成するために存在しており、目的を達成するためにルールを守る必要があります。
ルールの中には、目的の達成のために不必要なルール等の意味のないルールも存在しており、必要性を感じないルールは未だに多く残っています。
盲目的に「ルールはルールだから守らなければならない」と思うことは、ただの思考停止です。
ルールを守る理由は「ルールだから」ではありません。
ルールの意味を考え、きちんとルールの運用をできる人になりたいですね。
今回参考にした本になります。
六本木のルール展に行った時に購入したのですが、とても論理的で面白い内容でした。
ルールについて、より論理的に考えたい人にオススメの一冊です。